はじめに
ポゼッションサッカーと聞くと「パスサッカー」や「ビルドアップを大事にするスタイル」「綺麗に崩してゴールを狙う」といったパスを重視するサッカー、つなぐサッカーを思い浮かべる人が少なくないように見受けられます。
さらに、「美しい」「面白い」「攻撃的」といったイメージと結びつけられることも多いようです。
しかし、実際のところポゼッションサッカーの本質は“パスサッカー”や“美しい攻撃”にあるわけではありません。
そこで本記事で、ポゼッションサッカーの本質について迫っていきたいと思います。
確実性
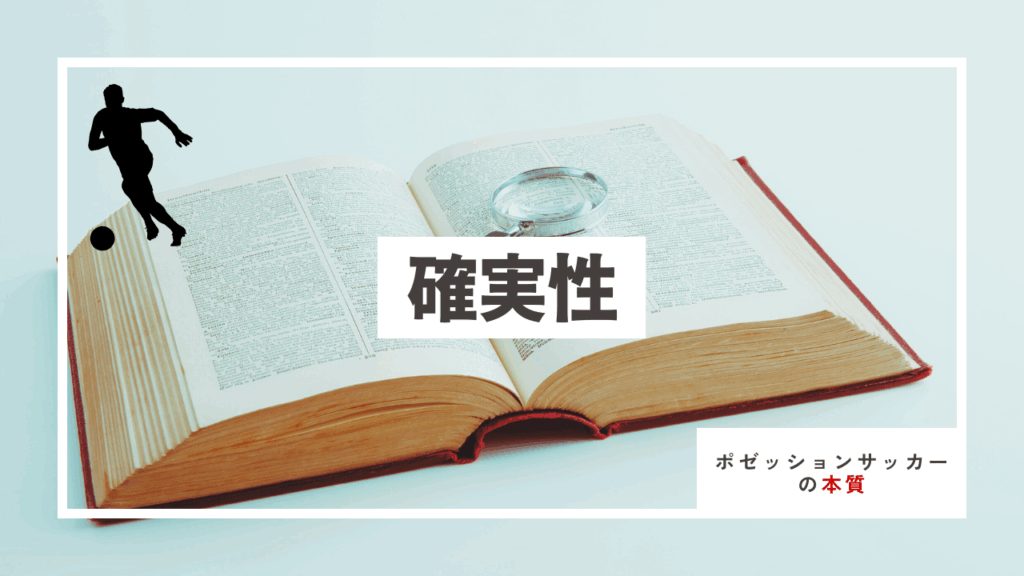
サッカーは当然ながらボールが一つしかありません。そのため、自分たちがボールを保持している限り、失点することは物理的にあり得ません。
しかし、相手にボールを持たれている状況では、ゴールを奪われるかどうかは相手次第になってしまいます。つまり、自分たちのコントロールが及ばない「他力的な状況」に置かれるのです。
一方でボールを保持している限りは「主体的な状況」にあります。ボール保持時に起こりうる「パスミスからインターセプトされる」、「ドリブルやボールキープに失敗しロストする」といったプレーは究極的には攻撃側がそのようなプレーを行わないようにすれば防ぐことができます。つまり他力的ではなく主体的な状況下でのミスに分類されます。
主体的な状況下ではそのようなロストそのものの回数を減らすことはもちろん、陣形内、ピッチ内のどの場所でのロストかといったロストの質も自分たち次第で向上することができます。例えばビルドアップ時に自陣で相手FWにパスをインターセプトをされた場合、危険度の高いショートカウンターとなります。このように「ロスト時の失点に結びつく危険度=質」も回数と同様に重要な要素であります。
主体的な状況下における悪いプレーの回数や質は自分たち次第でなくすことや改善することができるため自分たちのコントロール内にあります。
このような他力的な状況下の割合を減らし、主体的な状況下の割合を増やすことで結果として確実性の高いゲームコントロールを実現する一因となります。
以上のように当たり前のことではありますが、まずボールを保持している間は主体的な状況下であり、ゲーム内における他力的な状況、不確実性を減らすことができます。
能動性
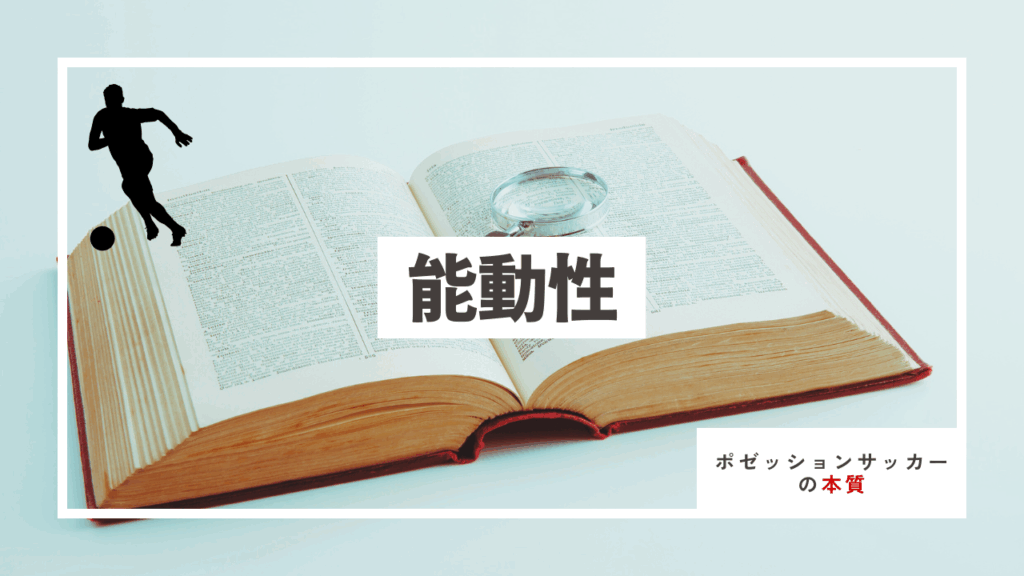
さらに陣形的な特性の面においても攻撃側、守備側で大きな違いが存在します。
陣形的な特性やフォーメーション論の詳細については、また別の機会に取り上げたいと思いますが、ここで一点だけ強調しておきたいのは、試合の中では常に攻守がその陣形に応じて「優位/劣位」の関係性にある、ということです。
攻守は互いに「優位」な側に回ることで結果として、良いプレーにつながる確率が高まります。攻撃側であれば効果的な前進、状態の良いオフェンスのチャレンジ(シュート、クロス、ドリブルなど)、守備側であればインターセプト、ボール奪取(デュエル)につながる可能性が高まります。
つまりサッカーという競技は、その特性として「全体の状況が部分の結果を左右する」構造を持っているのです。
その上で攻撃側、守備側の特性に決定的な違いがあります。それは、攻撃側は自分たち次第で優位な陣形を回復・維持できるということです。
攻撃側は自分たち次第で優位な側に回ることができる「能動性」を持つ性質があるのに対して、守備側が優位な側に回ることができるのは攻撃側次第であり、攻撃側次第で強制的に劣位な立場に回されます。つまり、攻撃側が「能動性」であることに対して、守備側は「受動性」であるということです。
サッカーはボール保持側が潜在的に有利な競技
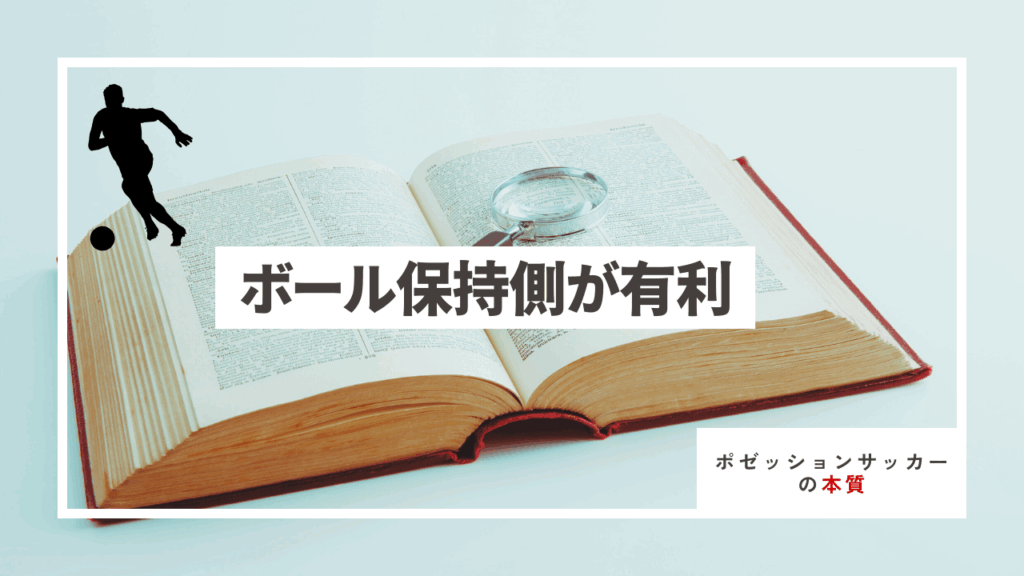
以上の二つの点から導かれる結論はシンプルです。サッカーという競技における普遍の真理として、ボールを持つ側が優位であることが大前提になるということです。
だからこそ、ボールを保持できる強者が、あえて「非保持=受動性」を選び、「保持=能動性」を放棄する理由はありません。自らボールを保持し、試合の中で優位な状態をできるだけ増やすことで、「質の良い機会を増やす → 良い結果が多くなる」という好循環を手にすることができます。
この大前提は、あらゆる戦術論を考える際にまず押さえておくべきポイントだと言えると思います。
例えば「相手に持たせるサッカー」や「構えるサッカー」は、守備から入るものの主体的な戦術かのように語られることがありますが、実際には他力的であり、受動性を帯びたサッカーです。サッカーにおいてまず重要なのは「ボールがどこにあるか」よりも前に、「自分たちがボールを保持しているか否か」という点なのです。なので安易に「相手に持たせる」と言われることに、個人的には違和感があります。それは、ボール保持の重要性が十分に認識されず、軽んじられていることの表れだと思います。
その上で力関係によって現実的な戦術として守備から入るサッカー、カウンターが選択されるのであると思います。「持てる試合」であえてボール保持を放棄することは、これまで述べたボール保持側が持つ優位性を手放すことでもあります。狙いがあっても、守備から入るサッカーはあくまで受動的であるということです。
戦術は自由選択ではなく、力関係により決まる部分が大きい
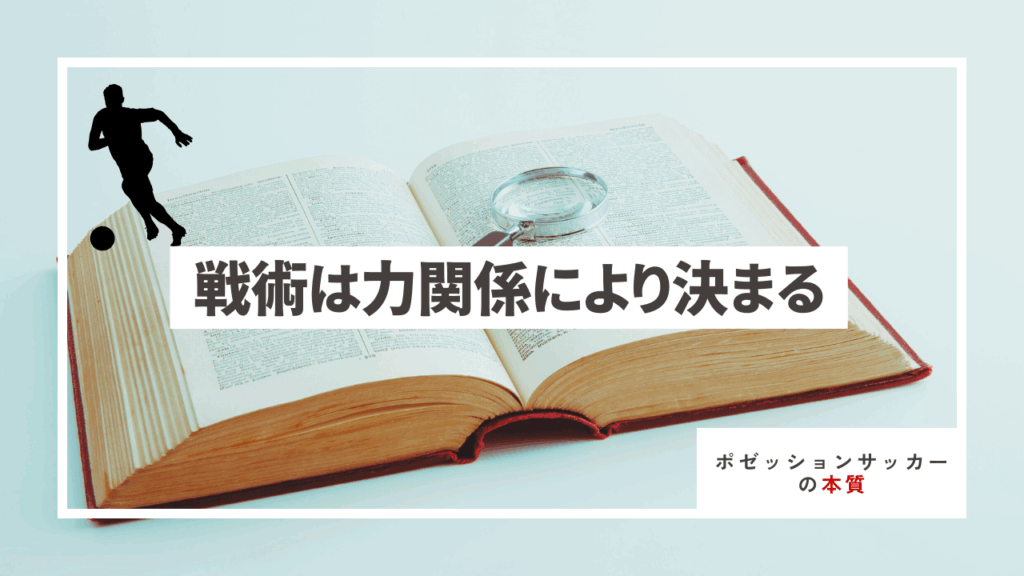
最後に強調しておきたいのは、ポゼッションや戦術といったゲームスタイルは、各チームが数ある選択肢から好みで選ぶものではない、という点です。実際にはチームの戦力差や相対的な力関係によって、ほとんど自動的に決まるものだと考えています。
試合における「強者」と「弱者」の構図の中では、一般的に強者はポゼッションサッカーを、弱者はカウンターサッカー(ショート〜ロング問わず)を採用する傾向があります。
強者側は、ボールを保持できる技術力をもった選手の質を擁しています。ビルドアップにおいても、質の低いチームであればショートカウンターを受けるリスクが高く、保持そのものがリスクになり得ます。さらに確実な前進はできたとしても、相手ゴール前でブロックが整った状況に行き着き、崩せないまま「持たされる」展開に陥ることも少なくありません。結果として、弱者は持つこと自体がリスク、崩せない、ということから守りから入りロングカウンターでスペースが豊富な状況での攻撃に活路を見出す、あるいは相手に持たせた上で奪いゴールに向かうショートカウンターなどで勝負するしかないのです。
一方、強者は弱者と比較して安定的なビルドアップ、そして押し込んだ状態でも得点力の計算が立ちます。キープ力に優れるウインガー、空中戦に強いセンターフォワード、パスに優れミドルを持つ10番、クロス精度の高いサイドバックなど、押し込んだ局面でもなお生きる選手が揃っているからです。
つまり、ポゼッションサッカーとは「ポゼッション率を重視するスタイル」ではなく、強者が本来の実力を順当に発揮するための最適なサッカーなのです。
ポゼッションサッカーの本質
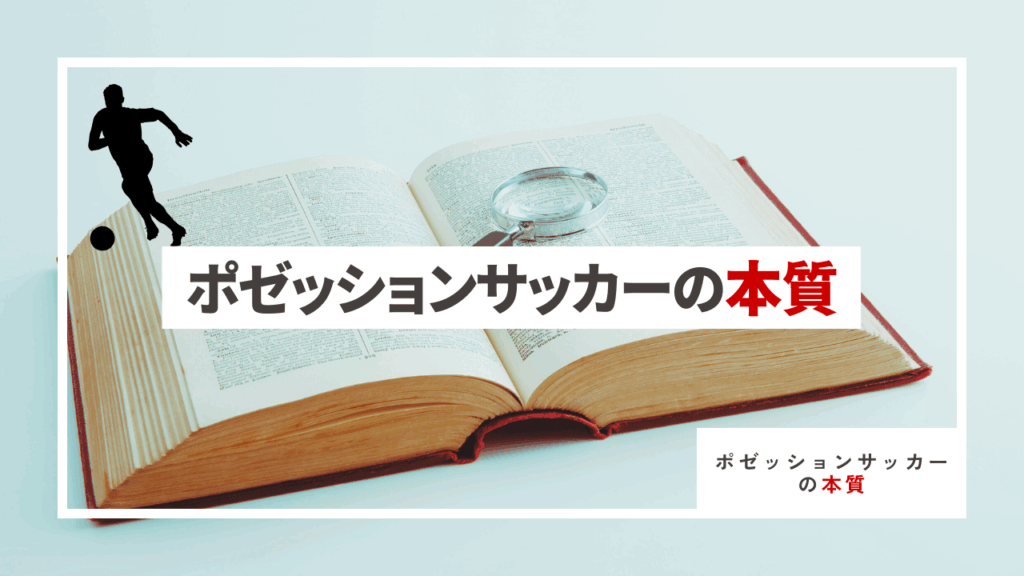
ここまでの点をまとめますとポゼッションサッカーの本質とはボール保持による特性である「確実性」と「能動性」にあります。
そして、強者側のチームが実力を順当に発揮するための最適なサッカーであります。
ポゼッションサッカーは「確実性」を重視するがゆえに、ショートパスやパス回しが多くなります。その結果として「美しい」「攻撃的」といった評価を受けることがありますが、これらはあくまで副次的な効果にすぎません。
たしかに、相手より長くボールを保持し、パス回しやドリブルといったアクションが数多く見られる時間が長いほど、プレーする選手にとっても観戦するファンにとっても魅力的に映るでしょう。
しかし、パス回しの多さ、オフェンスアクションの多さはあくまで結果として現れる要素であって、ポゼッションサッカーの本質ではありません。
そしてポゼッションサッカーは、相手よりもポゼッション率を高めること自体を目的とするものではありません。あくまで「確実性」を重視した結果としてポゼッション率が高くなる、これが本来のポゼッションサッカーとポゼッション率との関係性です。
ポゼッション率はあくまで結果にすぎず、それ自体に本質的な意味はありません。相手よりもポゼッション率が高かったからといって、必ずしも機能的なポゼッションサッカーが実現されたとは言えないのです。重要なのは数字ではなく、その中身の質にあります。確実性の高いゲームコントロールをベースにしつつ、質の高い機会創出を常に意識する。その上で、良い状態でのオフェンスチャレンジを狙い続ければ、自ずと中身の伴ったポゼッション率の過半を占めることにつながる。これがポゼッションサッカーの理想像であると思います。
ポゼッションサッカーが「パスサッカー」や「綺麗な崩しを目指すサッカー」「美しいから取り組むサッカー」といった印象で語られがちなのは、本来の姿が十分に理解されないまま、表面的に模倣されてきたことに原因があるのだと思います。
まとめ
- 主体的な状況を増やし、他力的な状況=不確実性の割合を減らすことにより、「確実性」を高められる
- 陣形的な優位性を「能動的」に維持・回復ができる
- サッカーは「ボール保持側が潜在的に優位な競技」である
- ポゼッション率より「中身の質」が重要
- 戦術は監督やチームの好みで自由に選ぶものではなく、「相対的な力関係によって半ば自動的に決まる」部分が大きい
今回は、サッカーを構成する数多くの要素の中から、構造的・原理的な観点に焦点を当てて考察しました。
実際の試合は多くの要因で成り立っており、今回はあくまでサッカーの原理的な性質・特性を示すことに主眼を置いたものであり一面的なものに過ぎません。余計な要因を取り払った上で、サッカーという競技の試合特性やポゼッションの本来的な姿を浮かび上がらせることを目的としました。それを知ることで、より解像度の高い試合観・戦術観を持つことにつながると考えています。
ここで示したのは「ポゼッションサッカーが正義である」とか「すべてのチームが取り組むべき戦術だ」という主張ではありません。あくまでサッカーにおける本来のポゼッションサッカーの姿やポゼッションサッカーの位置付けを整理したものです。基礎として理解しておくことで、サッカーの見方や考え方の幅が広がることが狙いです。
実際の試合における具体的な戦術や原理原則、再現方法などについては、今後も当ブログで順次発信していきますので、ぜひご期待ください。
最後までご覧いただきましてありがとうございました。
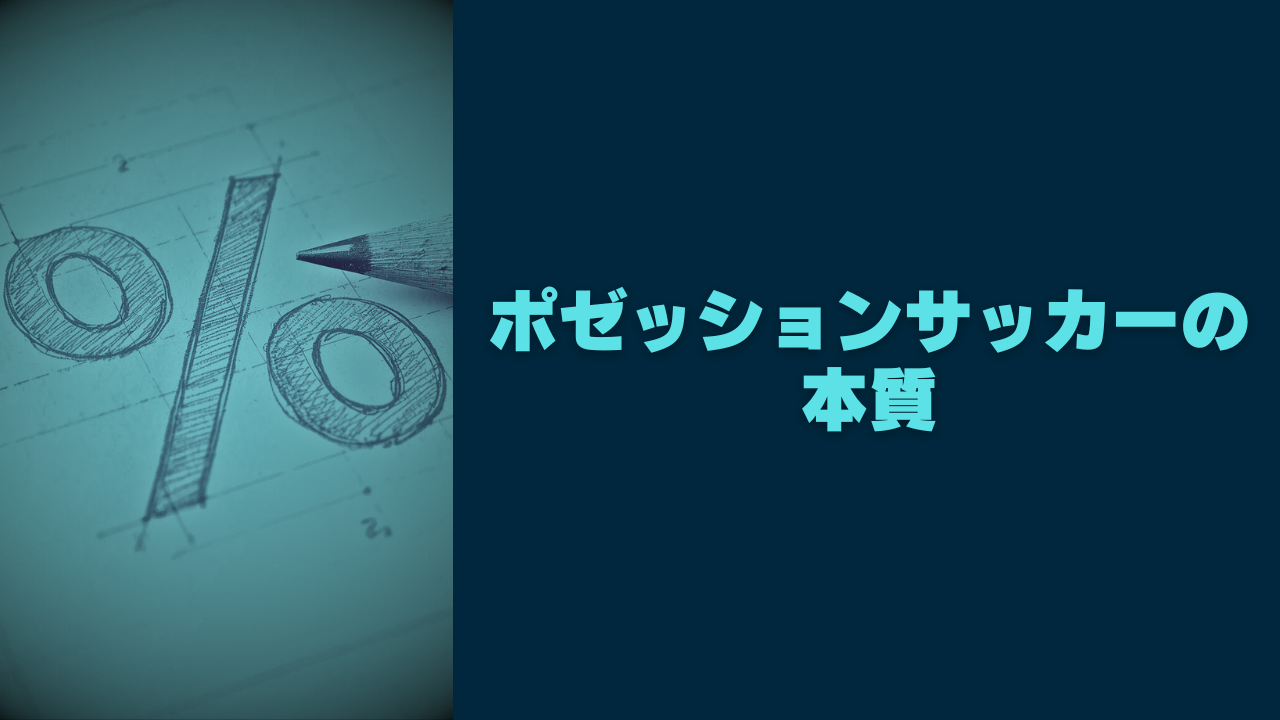


コメント